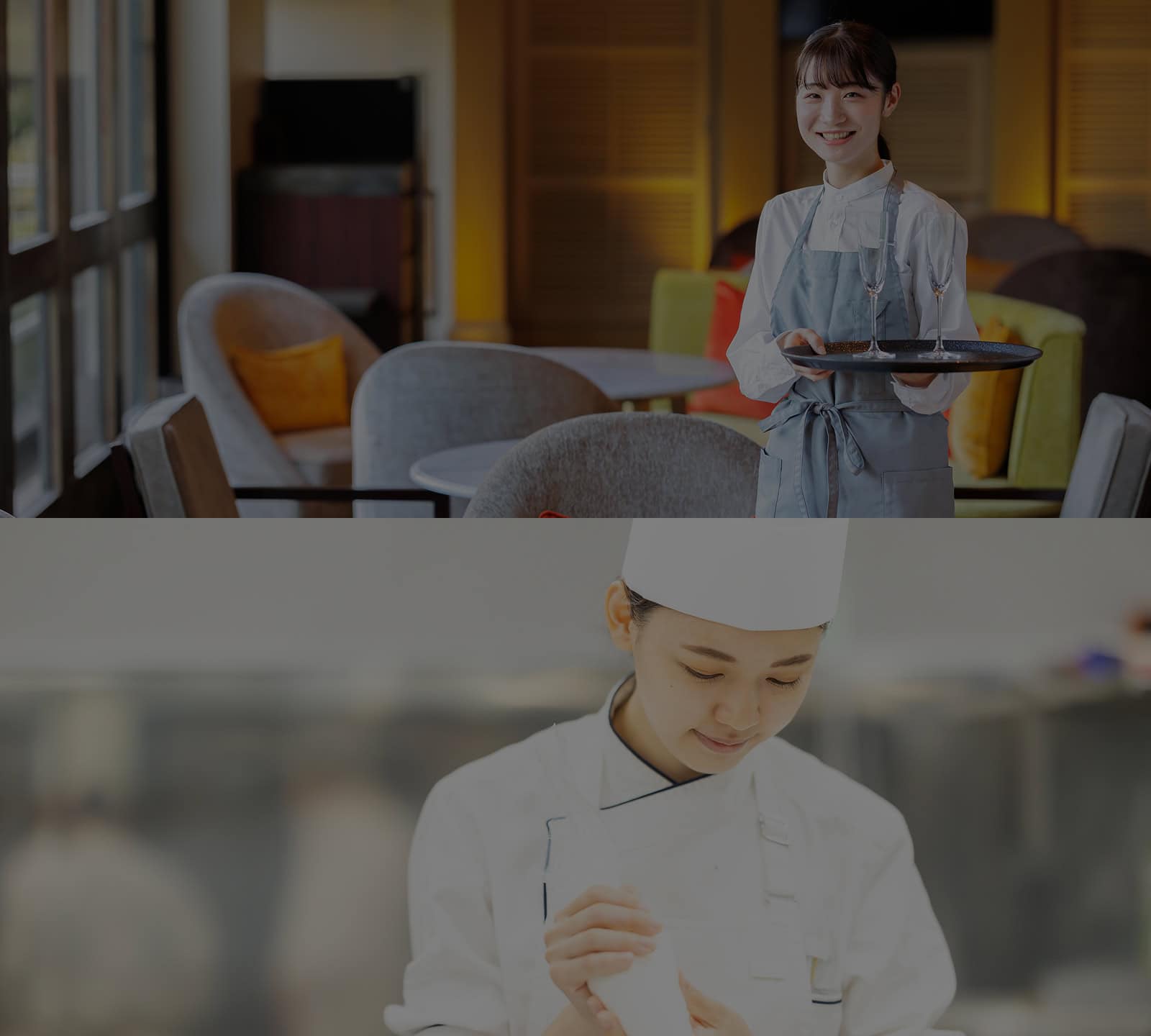飲食店が赤字になる原因5選|忙しいのに利益が出ない落とし穴
週末は満席なのに、月末の通帳を見ると赤字。
「あれ?こんなに忙しかったのに、なんで…?」
店を閉めた後、一人で電卓を叩きながら、首をかしげた経験はありませんか?
実は、赤字店舗には「見えにくい5つの原因」があります。
そして、その原因は、真面目に頑張っている経営者ほど気づきにくいのです。
なぜなら、その原因は「努力」や「情熱」とは別の場所にあるからです。
この記事では、多くの飲食店が陥る「5つの原因」を、データと具体例をもとに解説します。
もしあなたが、
「こんなに頑張っているのに、なぜ赤字なのか」
と悩んでいるなら、この記事がその答えを示すかもしれません。
あなたの店も、知らないうちにその原因の落とし穴にはまっていませんか?
飲食店の赤字は、あなたのお店だけではありません
「もしかして、経営者として自分が無能なんじゃないか…」
赤字が続くと、そう思ってしまう方は少なくありません。
しかし、まず知っておいてください。
飲食店の赤字は、あなた個人の能力の問題ではありません。
飲食業界は、構造的に厳しい
客観的なデータを見てみましょう。
開業から数年で、多くの店舗が姿を消している
民間の業界解説などでは、飲食店は「開業から数年のあいだに半数以上が廃業する」といった
データがしばしば紹介されています。
これは、「10店舗開業したら、数年後に残っている店は半分程度にまで減ってしまうことも珍しくない」という
イメージです。
離職率も他産業より高い水準
厚生労働省の調査でも、「宿泊業・飲食サービス業」は年間離職率が
全産業平均より明らかに高い水準で推移しています。
人が定着しにくい業界構造の中で、採用と育成に常に追われやすいのが飲食業です。
利益率も決して高くない
各種の業界レポートでは、飲食業の営業利益率は一桁台にとどまり、
製造業やIT関連などと比較すると「薄利」とされることが多い分野です。
「100万円売っても、経費を引いた後に手元に残る利益はそれほど大きくない」という構造に置かれています。
そして今、コスト増加の三重苦
原材料費:2年で平均20〜30%上昇
人件費:最低賃金の継続的な引き上げ
光熱費:エネルギー価格の高騰
この三重苦が、飲食店経営者を追い詰めています。
なぜこのデータを見せたのか?
ここまで読んで、
「やっぱり飲食店は厳しいんだ…」
と暗い気持ちになったかもしれません。
しかし、これらのデータを見せたのは、あなたを絶望させるためではありません。
伝えたいのは、
「赤字なのは、あなたの努力不足ではない。業界全体が構造的に厳しいのだ」
だからこそ、重要なのは「頑張り」ではなく、「どこに穴があるのかを正確に見つけること」なのです。
それでも黒字の店舗は存在する
ここで、一つの疑問が浮かびます。
「それでも、黒字を維持している店舗は存在する。その違いは、一体どこにあるのか?」
答えはシンプルです。
黒字店舗は、「5つの落とし穴」を避けているのです。
逆に言えば、赤字店舗は、
この5つの落とし穴のいずれか(または複数)にはまっています。
次の章で、その「見えにくい5つの落とし穴」を、具体的に見ていきましょう。
飲食店が赤字になる5つの原因と落とし穴
それでは、多くの飲食店が陥る「5つの落とし穴」を見ていきましょう。
これらは、決して分かりやすいような失敗ではありません。
むしろ、「当たり前」と思っている日常の中に潜んでいるからこそ、
気づきにくく、そして危険なのです。
あなたの店舗にも当てはまるものがないか、確認しながら読み進めてみてください。
飲食店の赤字は、あなた個人の能力の問題ではありません。
赤字の原因①:平日への甘い認識
「金曜・土曜は満席。でも月曜〜木曜は客がまばら」
こんな状況、身に覚えはありませんか?
多くの経営者は「週末で稼げているから大丈夫」と考えます。しかし、ここに落とし穴があります。
平日の赤字が、週末の黒字を食い潰す
日本政策金融公庫の調査(2019年)によると、飲食店の約7割が赤字経営です。
その多くが「週末は繁盛しているのに赤字」というパターン。
なぜか?
1ヶ月30日のうち、週末(金土日)は12日、平日(月〜木)は16日。
週末は黒字でも、平日が赤字なら、赤字の日の方が多いのです。
さらに、平日も週末と同じ人件費をかけていれば、固定費は確実に利益を食い潰します。
黒字店舗との違い
一方、黒字を維持している店舗は、平日も「稼ぐ日」に変えています。
赤字店舗:平日は「仕方ない」と諦めている
黒字店舗:平日限定メニュー、ランチ強化、人件費の最適化で「平日も稼ぐ」
平日をどう攻略するかが、黒字と赤字の分かれ目です。
セルフチェック
▢ 平日と週末の客数に大きな差がある
▢ 平日も週末と同じ人件費をかけている
→ 当てはまれば要注意
赤字の原因②:価格転嫁できない
「原材料が値上がりしているのはわかっている。
でも、メニューの価格を上げたら客が来なくなるんじゃないか…」
この葛藤を抱えている経営者は少なくありません。
しかし、価格を据え置いたまま耐え続けることこそが、赤字への最短ルートです。
コスト上昇を価格に反映できない店は潰れる
近年、原材料費、人件費、光熱費が軒並み上昇しています。
にもかかわらず、多くの飲食店は「値上げしたら客が減る」と恐れ、価格を据え置いています。
ある居酒屋の実例:
・競合店との価格競争に巻き込まれた居酒屋は、値下げで客数を増やそうとしました。
・確かに客足は伸びましたが、人件費や原価率の見直しは行わず、結果として赤字が拡大。
・廃業に追い込まれました。
値下げに頼るのではなく、適正価格での経営が不可欠です。
黒字店舗との違い
赤字店舗: 「値上げ=客離れ」と恐れて何もしない。
黒字店舗: コストが上がれば適正価格に見直す。同時に、価値を高める工夫(メニューの質向上、接客改善)を行う。
適正価格で持続可能な経営をすることこそが、顧客への誠実さです。
セルフチェック
▢ この2年で原価率が5%以上上がった
▢ メニュー価格を見直していない
→ 当てはまれば要注意
赤字の原因③:SNS活用の遅れ
「SNSが大事なのはわかっている。でも、毎日投稿する時間なんてない」
営業に追われる経営者にとって、SNS運用は後回しになりがちです。
しかし、今の時代、SNSで見つけてもらえない店は「存在しない店」と同じです。
情報発信をしない店は、選択肢にすら入らない
グルメサイトに頼るだけでは不十分です。
なぜなら、多くの消費者は「InstagramやGoogleマップの口コミ」を見て店を選ぶからです。
SNSを放置している店は、新規顧客との接点を自ら手放しているのと同じです。
ある飲食店の実例:
・一時的にSNSでバズったラーメン店がありました。
・しかし、話題性が収益に直結せず、オペレーションの混乱も重なり、結局は閉店。
・バズることと、継続的に集客することは別物なのです。
重要なのは、「継続的に情報を発信し、顧客との接点を保つ仕組み」です。
黒字店舗との違い
赤字店舗: SNSは「やった方がいい」と思っているが、手が回らず放置
黒字店舗:週に数回の投稿を習慣化。新メニュー、イベント情報、お客様の声などを発信し続ける
SNS運用は「特別なこと」ではなく、「当たり前の集客活動」です。
セルフチェック
▢ SNSを3ヶ月以上更新していない
▢ Googleビジネスプロフィールを整備していない
→ 当てはまれば要注意
赤字の原因④:スタッフがすぐ辞める負のループ
「やっと育てたスタッフが、また辞めてしまった…」
飲食業界の離職率は約70%。全産業平均の約15%と比較しても、突出して高い数字です。
スタッフが定着しない店は、慢性的な人手不足に陥り、悪循環から抜け出せなくなります。
人が辞める→オーナーが疲弊→サービス低下→また人が辞める
スタッフが辞めると、残ったメンバーの負担が増えます。
オーナー自らがワンオペ状態になり、疲弊していきます。
その結果、接客の質が下がり、料理の提供が遅れ、お客様の満足度が低下。
悪い口コミが広がり、新規客も減少します。
そして、過酷な労働環境を見た新しいスタッフも、すぐに辞めていく…
この負のループに一度入ると、抜け出すのは非常に困難です。
黒字店舗との違い
赤字店舗: 「人が辞めるのは仕方ない」と諦めている
黒字店舗: スタッフが働きやすい環境づくりに投資。適切なシフト管理、休日確保、コミュニケーションを重視
人材への投資を惜しむと、結果的により大きなコストを払うことになります。
セルフチェック
▢ この1年で3人以上のスタッフが辞めた
▢ オーナーが週6日以上働いている
→ 当てはまれば要注意
赤字の原因⑤:効率化の遅れ
「注文は手書き、在庫管理はノート、シフトはホワイトボード…」
アナログな運営方法に慣れている経営者ほど、デジタル化を避ける傾向があります。
しかし、効率化の遅れは、目に見えないコストとして経営を圧迫し続けます。
「今のやり方で回っている」という油断が命取り
手書きの注文はミスを生み、在庫管理が曖昧だと食材ロスが増え、
シフト調整に時間を取られれば経営に集中できません。
これらは一つひとつは小さな問題に見えますが、積み重なると大きな利益損失になります。
さらに、アナログ運営は「スタッフへの負担」も増やします。
非効率な仕組みの中で働くスタッフは、ストレスを感じ、離職につながります。
黒字店舗との違い
赤字店舗: 「今のやり方で回っているから問題ない」と現状維持
黒字店舗: POSレジ、予約管理システム、勤怠管理ツールなどを導入。オーナーは経営に集中できる時間を確保
デジタル化のコストを「投資」と捉えるか、「無駄な出費」と捉えるかが、明暗を分けます。
セルフチェック
▢注文や会計を手書きで管理している
▢在庫管理や売上分析をしていない
→ 当てはまれば要注意
飲食店の赤字対策を実行できない理由
ここまで読んで、5つの落とし穴に気づいた方も多いはずです。
「そうか、これが原因だったのか」
しかし、同時にこう思ったのではないでしょうか?
「わかっているけど、実行するのは無理だ」
その感覚は、正しいです。
なぜなら、この5つの対策を一人の経営者が、営業しながら実行するのは、現実的に不可能だからです。
なぜ実行できないのか?
理由1:時間がない
朝の仕込みから夜の片付けまで、経営者は12〜16時間働いています。
その合間に、平日集客の施策を考え、SNSを毎日投稿し、スタッフ採用の面接をし、
デジタル化のツールを比較検討する… 物理的に不可能です。
理由2:専門知識がない
「SNS運用」一つとっても、どのプラットフォームを使うべきか、
どんな投稿が効果的か、効果測定はどうすればいいのか。
料理のプロである経営者が、マーケティングや人事、財務のプロでもあることは稀です。
理由3:優先順位がわからない
5つの対策、どれも重要に見えます。しかし、全部を同時に実行することはできません。
「うちの店は、何から手をつけるべきなのか?」
この判断を誤ると、貴重な時間とお金を無駄にしてしまいます。
理由4:一人で抱え込んでいる
スタッフに任せようにも、すぐ辞めてしまう。結局、経営者が全部やるしかない。
しかし、一人でできることには限界があります。
だからこそ、専門家のサポートが必要
飲食店経営の専門家は、何百という店舗を見てきた経験から、あなたの店舗に最適な優先順位を判断できます。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りること。
それが、赤字の落とし穴から抜け出す最短ルートです。
飲食店の赤字脱却には専門家のサポートを
私たちは、飲食店経営者の「わかっているけど、実行できない」をサポートする専門家です。
一人で抱え込む必要はありません。
赤字の原因がわかっても、対策を実行できなければ状況は変わりません。
まずはお気軽にご相談ください。