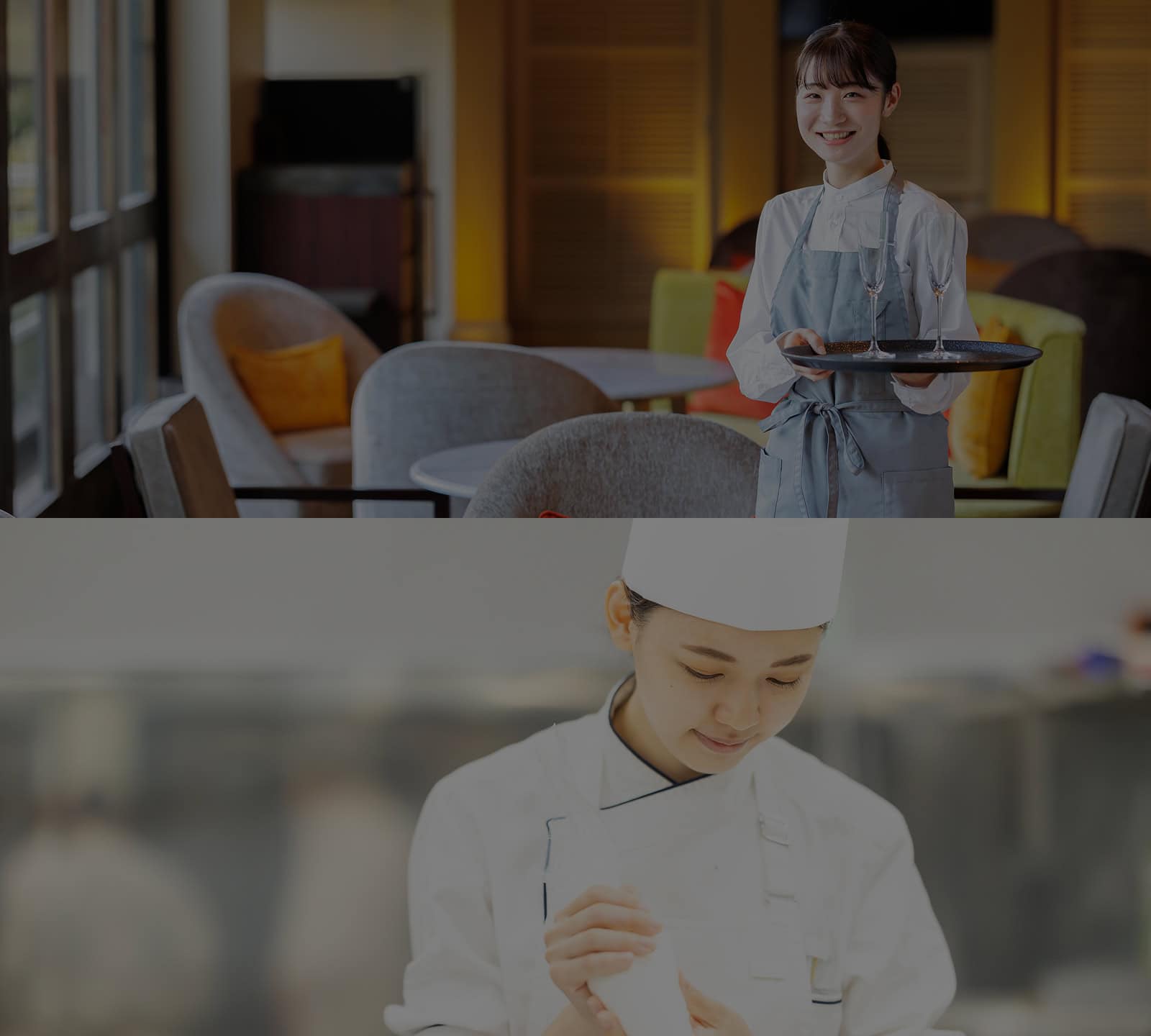【2025年最新】飲食店開業に必要な資格は2つだけ!
調理師免許は必要?不要?
調理師免許は、絶対に必要だ?
正解は×です。
飲食店経営において、必ず調理師免許の資格が必要というわけではありません。
しかし、全くの資格なしに飲食店をオープンできるわけではありません。
飲食店経営に必要な資格は2つあります。
飲食店開業に必要な資格は2つだけ
飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者(収容人数30名以上の場合)」です。
「収容人数が10人しかいないし、防火管理者は入らなくて良い。」と考えるのは推奨しておりません。防火管理者の講習は座学だけではなく、実技も行います。自身を含めた人の命を預かる立場として受けておくと、その後の従業員や危機管理に役立ち万が一に備えられて初めて責任のある経営になります。「収容人数が10人しかいないし、防火管理者は入らなくて良い。」と考えるのは推奨しておりません。防火管理者の講習は座学だけではなく、実技も行います。自身を含めた人の命を預かる立場として受けておくと、その後の従業員や危機管理に役立ち万が一に備えられて初めて責任のある経営になります。
■食品衛生責任者(全店舗必須・約10,000円・1日講習)
食品衛生責任者の資格は必須です。
開店前に必ず取得しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を6時間程度受ければ取得できます。
受講費は約10,000円です。
■食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは食品衛生法で定められた営業所において、衛生管理などを担う者を指します。
飲食店や食品販売など、許可や届出が必要な施設には必ず食品衛生責任者の存在が必要です。
この資格は、店舗のオーナー自身が取得することも可能ですし、従業員の中から資格者を1名選任することもできます。
ただし、1名の食品衛生責任者に複数店舗を任せることは禁止となっています。
■防火管理者(30名以上収容・6,500円~・1~2日講習)
防火管理者の資格も開店前に必ず取りましょう。
飲食店の場合、収容人数が30名以上(従業員も含め)になると防火管理者の資格が必要になります。
収容人数とは、お客様の数ではなく従業員も含めた数です。
地域や人数によって料金が異なりますが、店舗などの防火対象物が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者、300㎡未満の場合は乙種防火管理者の資格が必要になります。
甲種防火管理新規講習が7500円で、2日講習
乙種防火管理新規講習が6500円で、1日講習
自治体によって異なる場合がございますので、必ず自身で、調べてから資格を取得しましょう。
■防火管理者とは?
防火管理者とは消防法に定められた国家資格です。
一定規模以上の施設になると、必ず防火管理者の選任が義務づけられています。
また、規模などによって防火管理者の数や資格の種類が異なります。
防火管理者は従業員を、管理、総括できる地位で防火対象物の管理、予防、消火活動を行える者に限られます。
自治体によって異なる場合がございますので、必ず自身で、調べてから資格を取得しましょう。
調理師免許は開業に必須ではない理由
■食品衛生責任者は必須だが、調理師免許が必須なわけではない。
調理師免許は国家資格であり、食品衛生法に基づいてつくられており、食の安全を守り、衛生管理を学べる資格となっています。
そのため調理師免許を取得すると、食品衛生責任者は申請するだけで取得できます。また、「調理師」を名乗ることができます。
※調理師免許を取得していない人が、WEBやSNS等で「調理師」を名乗る事は違法になります。
しかし、調理師免許はあくまで調理師であることを証明するものであり、飲食店の経営に必須なものではありません。
■衛生管理ができていれば問題ない
飲食店を経営するにあたり、食品衛生責任者の設置は必須になります。ここで、多くの方が誤解を生じるポイント!
①必須になるのは「食品衛生責任者」を取得している人が在籍していること
②調理師免許を持っているだけでは、飲食店の運営は出来ない。
③調理師免許を取得している人でも、「食品衛生責任者」の申請をして、資格を取得する必要がある。
調理師免許においても衛生管理を学びますが、食品衛生責任者の資格が、自動で付いてくるものではありません。
必ず申請を行う必要があります。
調理師免許をもっていれば食品衛生責任者の資格を取る必要はありませんが、食品衛生責任者の資格は2日講習を受ければ取れる資格なので、
そのために調理師免許の資格を取る必要はありません。
■調理師免許を持っている人を雇うという選択肢
飲食店経営をするにあたって、調理師免許を持っている人を雇うという選択肢もあります。
調理師免許を取得するには、各自治体で指定された養成所に通い、所定の課程を修了するか、調理師試験に合格する必要があります。
大抵は受験資格として2年以上の調理業務経験が求められます。
簡単に取れる資格ではないからこそ、調理に精通した素晴らしい人材を確保できる確率が高くなります。
規模別・業態別の必要資格
■小規模飲食店(30名未満)の場合
先程も記述しましたが、小規模飲食店(従業員含め30名未満)の場合、乙種防火管理の資格が必要ですが、
もしこれから事業展開をしていって、大規模な店舗を作りたいと考えている場合は、今のうちに甲種防火管理の資格を取っておくのも良いでしょう。
■居酒屋やバーなどの深夜営業店の場合
酒類をメインに提供する飲食店が深夜0時以降も営業をする場合、店舗の所在地を管轄する警察署で「深夜酒類提供飲食店営業」の手続きをおこなう必要があります。深夜に酒類を提供する場合、近隣住民への配慮が必要になるため、風俗営業法に基づき、深夜帯の営業を管理、監視するために作られた規則です。
深夜営業かつ、酒類を提供する場合は、必ず深夜酒類提供飲食店営業の手続きを行ってください。
■特殊食材店(ふぐ料理等)の場合※特殊素材取り扱いの免許必要+必須資格2つ必要
就業した際の「年間休日数」や「報酬」などの労働条件を応募者が面接官に質問しても、その質問に対し、明確に回答しない、もしくは回答をはぐらかす。このような企業はブラック企業の可能性が高いです。しっかりとした年間休日を労働者に与えていて、報酬に関しても法令に則ったものを提供している企業であれば、質問に対し自信をもって回答できるはずですし、できて当たり前です。
年間休日数や報酬といった、労働者が最も疑問とする質問に対して、明確な回答ができない企業は就労しない方が良いでしょう。
◆ふぐ料理の場合
ふぐ料理などの特殊食材を扱うには注意が必要です。
ふぐ料理を提供する場合は、必須資格とは別でふぐ調理師免許が必要です。
ふぐ調理師免許は、調理師免許を取得したのち、ふぐ調理師の有資格者の元で2年以上従事し、各都道府県で制定したふぐ条例の元、学科と実技によるふぐ調理師試験を受験する必要があります。
◆ジビエや生食用食肉を扱う場合
飲食店や販売店でジビエ(野生鳥獣の肉)を扱う場合は、食品衛生法に基づく食肉処理業の営業許可を取得した施設で解体された肉を仕入れなければなりません。
また、生食用食肉は規格基準を満たし、都道府県知事の許可を得る必要があります。
ジビエ(野生鳥獣の肉)を扱う場合は、食肉処理業の許可
生食用食肉:生食用食肉の規格基準を満たし、都道府県知事の許可を得る必要があります。
資格取得の具体的な方法と費用【2025年最新】
■食品衛生責任者の取得手順
食品衛生責任者の取得手順について見ていきましょう。
食品衛生責任者になるには、栄養士や調理師などの資格を取得する方法と、資格者養成講習会を受講するという2つの方法があります。
◆資格者養成講習会の内容
食品衛生学(2.5時間):
食中毒などの発生を防止する基本的な対応を学びます。
食品衛生法(3時間):
食品衛生法の基本的な座学です。
業務者の責務など自主的な衛生管理に関すること、自主回収報告制度、営業規則(許可、届出、施設基準)などを広く学びます。
公衆衛生学(0.5時間):
環境衛生、労働衛生など
確認試験:
最後はこれまでの知識の定着度や理解度を確認する試験があります。
上記の講習会や試験を含めトータルで6時間ぐらいかかります。
◆防火管理者の取得手順
防火管理者になる方法のひとつとして、大学や短期大学、高等学校などで防災関連の学科や課程を修了、卒業し、さらに1年間防火管理の実務経験をすると、防火管理講習を受けなくても防火管理者として認められます。
防火管理者の資格は、防火管理の学歴と実務経験があることの証明を、管轄している消防署に提出すれば得ることができます。
■資格取得のスケジュール例
防火管理講習のスケジュール例を紹介します。
◆甲種の講習内容
甲種の場合は10時間の講習があり受講するには2日間を要します。
具体的な内容は以下の通りです。
・防災管理の意義、および制度について
・火災の基礎知識、危険物の安全管理、地震対策を含む火気管理
・施設、設備の維持管理
・防火管理に関係する訓練、教育
・防火管理に関する消防計画
◆乙種の講義内容
乙種の講義内容は5時間で終了します。
そのため、講義は1日で完結します。
講義の内容は甲種の基礎的な知識や技術に関することを学びます。
講義の時間は甲種の半分ではありますが、重要な部分を押えているのでしっかりと勉強しましょう。
甲種、乙種のいずれも最後に効果測定(試験)があります。講義で習ったことをしっかり覚えましょう。
飲食店開業に必要な届出・手続き一覧
■保健所への届出
保健所にて「飲食店営業許可」の取得が必要です。内装工事が完了する10日前までに保健所に必要書類を持っていきましょう。
その後、店舗確認検査があります。こちらはオーナーもしくは代理人の立ち会いが必要です。
そして無事基準を満たしていたら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。
許可証が交付されたら、営業が開始できます。
許可申請の代理は可能です。
中には行政書士に頼む方もいらっしゃいます。
■消防署への届出
消防署にはいくつかの書類の提出が求められます。
・防火対象物使用開始届
・防火管理者選任届
・消防設備などの設置届関連
・消防計画や防火管理関係の書類
こちらも書類の届出を代理するビジネスなどもあるため、代理の提出は可能です。
■警察署への届出
警察署に提出が必要となる届出は以下の通りです。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
・風俗営業許可申請
・特定遊興飲食店営業許可申請
こちらも行政書士への代行が可能です。
■税務署への届出
税務署には開業届を提出します。
基本的には開業する本人が届出を出すことになっていますが、親族や税理士の代理提出は可能です。
■税務署への届出
税務署には開業届を提出します。
基本的には開業する本人が届出を出すことになっていますが、親族や税理士の代理提出は可能です。
飲食店開業資格クイズ
ここまでのおさらいとして飲食店の開業資格クイズをおこないます。
■飲食店を開くには何の資格が必要ですか?
答え:食品衛生責任者、乙種防火管理者
■調理師免許が無くても飲食店を開業できますか?
答え :開業可能です。
飲食店の開業に必ずしも調理師免許が必要な訳ではありません。
◆1日だけ飲食店を開業するにはどんな資格が必要ですか?
答え :開業可能です。
飲食店の開業に必ずしも調理師免許が必要な訳ではありません。
まとめ
これまで、飲食店経営に必要な資格をご紹介しました。
飲食店経営には様々な資格や届出が必要なので、大変に思えるかもしれませんが、ひとつひとつ取り組めばきっと大丈夫です。
大変に感じたら、一部を行政書士や税理士に任せることもできるので検討してみましょう。
もし、資格取得のタイミングや必要な資格を持つ人材の確保といった人材面での課題、あるいは開業後の店舗展開を見据えた際の資格に関するご相談など、お困りのことがございましたら、ぜひ八芳園ヒューマンリソースマネジメントにお気軽にご相談ください。
飲食店経営に精通したプロが、お客様のビジネスの成功に向けて、マンツーマンで課題解決をサポートいたします。
私たちと共に、飲食店経営の夢を叶えましょう。
八芳園ヒューマンリソースマネジメントの想い
飲食店経営は開業まで大変ですが、私たち八芳園ヒューマンリソースマネジメントが尽力を尽くしサポートいたします。
飲食店経営に精通するプロ集団が現地に赴き、マンツーマンで課題解決をし、必ずあなたのビジネスを成功させます。
一緒に飲食店経営を成功させる夢を叶えましょう。
▶お問い合わせはコチラ◀
八芳園ヒューマンリソースマネジメント
https://happo-en-hrm.co.jp/